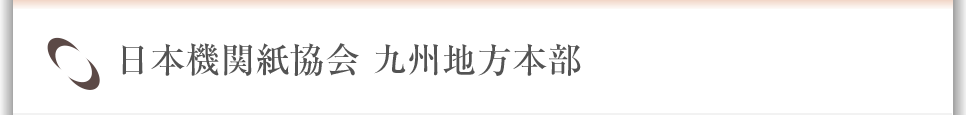悲惨な歴史を受け継ぐ
三苫 哲也(55歳) 福岡市博多区 福岡医療団労働組合
悲惨な歴史を受け継ぐ
その姿を思い起こせば、何がなんでも戦争をやめさせなければならないと、考えが及ぶのではないでしょうか。しかし、そうは言っても、なかなか戦争の悲惨さをイメージすることは難しいのかもしれません。ゲーム感覚でリアルな戦争ゲームも流布していて、逆にバーチャル空間に戦場がなってしまっているのかもしれません。
私は、だからこそ、平和学習、語り部の方のお話を若い世代でも口承していく、実相を現した反戦映画を見る、「はだしのゲン」を読む、こうしたことが本当に大切になってくるのではないかと思います。
日本が戦争に負けて80年という年月が経ち、先の戦争の悲惨な状況をなかなか伝えられない状況ではありますが、しかし、至るところで若い人たちが継承にむけて立ち上がっています。私も、福岡市の戦跡巡りを福岡の戦跡の著書である首藤たくもさんから案内していただき、その後、著書をよみ、また博多の歴史なども話を織り交ぜ、福岡大空襲の実態と博多の歴史として、ガイド活動をしています。
ただ、一方で危うさもあります。戦争映画は反戦の衣を装いながらも実際に見てみると特攻が美化されていたり、特に若い人に人気の役者の映画などにその傾向があるようですが、ここは注意しないといけないところだとも思います。私もお話をしながら、事実と私の感想、当時逃げ惑った母の実際の言葉と、それを聞いた時の私の気持ち、など、明確にしながらも、悲惨さを伝えるという作業の難しさも感じます。それでも、今の僕らの世代がリアルに悲惨さを継承し伝えていくことは本当に世界平和につながる大いなる活動だとも思います。ぜひ皆さんができるところからやっていきませんか。