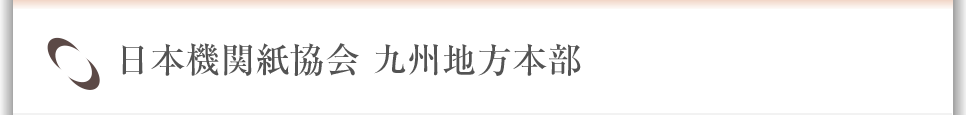戦争を知らない時代に生まれた私たちについて
匿名(27歳) 北九州市八幡西区
戦争を知らない時代に生まれた私たちについて
私の曾祖父も戦争体験者で、帰還兵でもありました。幼少期から可愛がってもらい、私も曾祖父を愛していましたが、日常の中で戦争に関する話を持ち出すことはしませんでした。何故なら、小学校に入学してからは夏が近づくと平和学習があり、幼いながらに戦争が悲惨なものだという印象が確かにあったからです。戦争体験者である曾祖父が貴重な存在であることはわかっていましたが、曾祖父に辛い記憶を思い出させることはしたくなかったため、意図的に戦争の話題は避けていました。
しかし、今では話を聞いておけばよかったのではないかと考える時があります。戦争の辛い記憶を、曾祖父だけでなく家族である私も一緒に抱えることができたのではないかと思ったのです。平和な時代に生まれた私では実際に戦争の苦しみを理解することはできませんが、それでも何か曾祖父に寄り添うことができたのではないかと後悔しています。曾祖父は認知症を患うこともなく100歳以上生き、最期は病院で穏やかに息を引き取りましたが、曾祖父にとって今の日本はどう見えていたのでしょうか。平和な日々を噛み締めていたのでしょうか。それとも、戦争の傷跡と記憶が薄れていくことを不安に思っていたでしょうか。それを問わなかった後悔を私はこれからも忘れたくありません。
戦争体験者は2020年代では約1%未満、2040年頃には0になると言われています。私たちは彼らの体験を知り、語り継ぎ、次の世代に繋いでいかなければなりません。ただ話を聞くだけでなく、多様な形で記録し、多くの人が触れられるよう発信する環境を整える必要があります。文字に書き起こしたり、戦争体験者の写真や動画を撮影したり、さまざまな記録媒体で保管し、それらの資料をどこにいても、どんなときでも、知りたい人が調べられる環境が理想だと考えています。しかし問題点もあります。デジタル化が発展した現在では、ほとんどの人がスマートフォンやパソコンでインターネットにアクセス可能であると同時に、情報伝達が異様に速く膨大な情報を目にすることになり、その情報が信頼できるのかどうか判断しなければなりません。戦争の貴重な記録を残しても、偽の情報と混ざってしまっては正しく伝わりません。また悪意によって書き換えられてしまう可能性もあります。仮に私の曾祖父の記録があったとして、それを第三者に上書きされたり別の事で利用されたりするようなことがあったら、私は許せないと思います。だからこそ、実際に戦争を体験したことがない私たちの役割は、戦争体験者の想いを正確に伝え、彼らの尊厳を守り続けていく意識と環境を広めることだと感じました。難しい課題だとは思いますが、私自身これからも向き合い続けていきたいです。